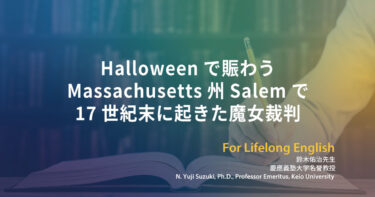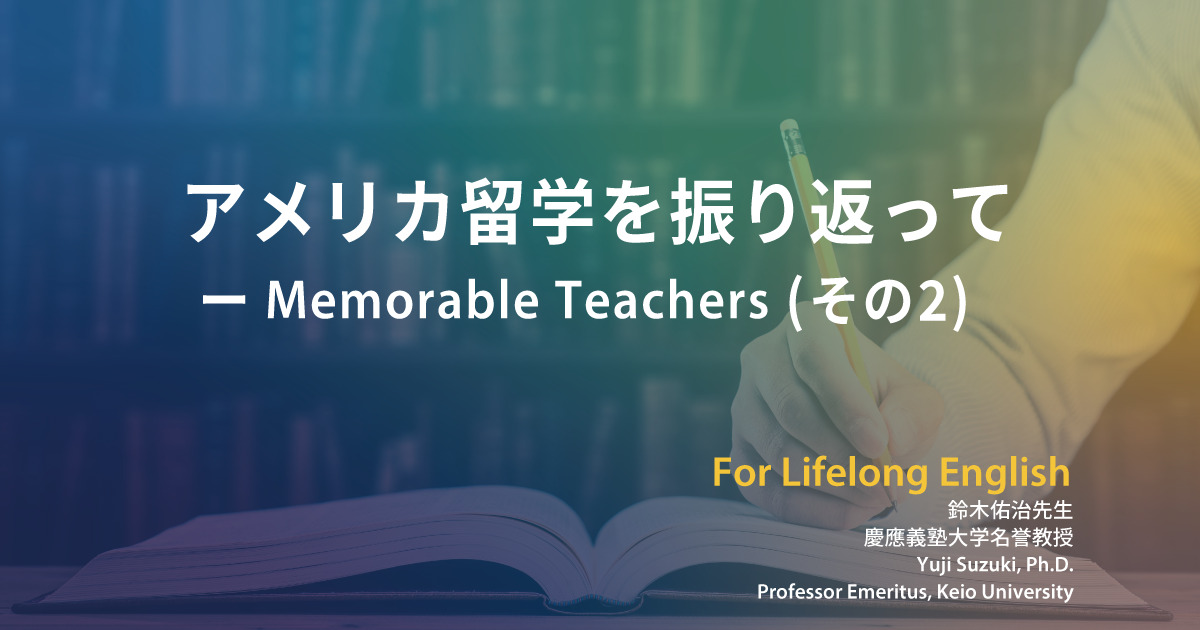
本コラム第133回「アメリカ留学を振り返って- Memorable Teachers(その1)」の続きです。
三日三晩のGreyhoundでの長旅は終点Los Angeles(LA)のダウンタウンで終わり、Santa Barbara行きのバスに乗り換えました。何車線も入り組んだ高速道路から見る夜のLAはキラキラ輝いていました。2時間ほどでSanta Barbaraのダウンタウンに着き、近くのホテルで一泊しました。
1969年9月20日前後であったと記憶していますが、その翌日の早朝、University of California at Santa Barbara(UCSB)のキャンパスがあるGoleta(*1)に向かいました。UCSBは当時Quarter制で新学年度最初のFall Quarterは10月1日から始まります。GoletaはUCSBのキャンパスタウンで、学生用のアパートやレストランなどの商業施設が立ち並び、新学期を間近に控えた通りは学生で溢れていました。西には太平洋が開け、街はそれを見下ろす小高い丘の上に広がり、丘の下には綺麗なビーチが横たわっています。キャンパスの中には海水と川の水が混じるラグーン(lagoon)があり、東にはSanta Barbaraを囲むように延々と続く山並みが迫り、誠に風光明媚な場所です。太平洋の彼方に消えゆく夕日はとても雄大でした。
その2ヶ月ほど前にLouisiana State University(LSU)にいた頃、UCSBのInternational House(I House)(*2)の空き部屋について問い合わせたところ、一通の手紙を受けとりました。フルネームを失念しましたが、MikeというUCSBの学部生からです。東洋哲学を専攻しており日本人ルームメイトを探しているとのこと、渡りに船とばかりにすぐさま同意の手紙を送りました。
指定された場所に行くと、MikeはTomというアジア系の学生と一緒に迎えにきてくれました。Tomの苗字は「ソーエンソン」、スペルはSorensonでしょうか。幼くして朝鮮動乱の最中に両親を失ったとのこと、右足に被弾した為に切除し、義足を付けていました。「ソーエンソン」というアメリカ人に引き取られ、アメリカで初等・中等教育を受け、UCSBに進学してEnglish(英米文学)を専攻し、来年はStanford University、UC Berkeley、Harvard Universityのいずれかの大学院に進むとのことでした。(*3)
MikeもTomもとても親切で筆者をあちこち案内してくれました。Mikeに日本人のルームメイトを探すように勧めたのはTomであったようです。Mikeは、筆者が日本で英文学修士号を持ちながらUCSBの大学院に進めないことに疑問を呈し、Graduate Admissions Officeに理由を聞きに行こうと言い出しました。前回述べた通り、当時、英語圏からの帰国子女やアメリカン・スクールの卒業生などを除き、英米文学科を専攻する日本人留学生は稀でした。(*4)日本の大学や大学院で英米文学を専攻しても、アメリカの大学院で英米文学専攻に要する英語力を備えるのは至難の業です。LSUのHead of the English Departmentの指摘はまさに図星なのです。ありがたいと思いつつも、Mikeの申し出にはあまり乗り気ではなかったのですが同行することにしました。
案の定、窓口の30代の女性職員はMikeを突っ放すかのようにあしらい始めました。曰く、“Did anyone (in the English Department) say he should’ve been accepted to the graduate English program?”Mikeは何も答えられず戸惑うばかりです。ルームメイトとは言え、赤の他人である筆者の為にこのような屈辱を味わう姿に深く痛み入りました。“Mike, that’s OK.Let’s go.Thank you anyway.”そう言いながらMikeの肩を軽く叩いて外に出ました。女性職員の言う通りです。これからなんとか努力して英語・英米文学でPh.D.を取って日本に帰りたい。今の自分にはその英語力は無い、日本で言えば武者修行のつもりで腕を磨きたい、日本人と日本文化を愛するMikeでしたからその心を分かってくれた筈です。その時に頭に響いたのは大好きなGeorge Lewisが演奏する次の曲でした。
“Over the Waves”(*5)
10月に入りいよいよ新学年度のFall Quarterが始まりました。Goletaのキャンパスタウンには、homecomingも兼ねてCollege Footballの試合を告げるブラスバンドが練り歩き、陽気で明るいアメリカを彷彿させるかのようです。他方、テレビではベトナム戦争のニュースが流れ、前線での激しい戦闘シーンが放映されていました。同じアメリカ人でありながら一方は殺戮の場に、一方は饗宴の場に?というギャップに戸惑いました。大学にいる限りは徴兵(draft)されませんが、ドロップアウトすると徴兵されてベトナム行きという時代です。学部生が大学に残るためには平均C(GPA2.0)以上の成績、大学院生はB(3.0)以上の成績が必要とされました。
成績(grades)は、A(Excellent=4.0)、B(Good=3.0)、C(Fair=2.0)、D(Poor=1.0)、F(Failure=0)の5段階です。例えば、Fall Quarterに4単位(credits)の授業を4つ取り、それぞれの成績がA、B、C、Dである場合、(4×4)+(4×3)+(4×2)+(4×1)=40になり、それを総単位数16で割りGPAを出します。この場合のGPAは40÷16=2.5です。Winter Quarterでも同じく4creditsの授業を4つ取り、成績がC、D、D、Fであったら、(4×2)+(4×1)+(4×1)+(4×0)=16で、この学期のGPAは1です。ここで2学期通算のGPAが計算され、1.75になってしまいます。すると、OfficeからGPAが足りないことを警告されて”On probation”になり、次の学期までにGPA2.0以上に改善しないと退学”Flank out”になります。次の大学を探してacceptされてtransferできなければ徴兵ということになります。
院生の場合はGPA3.0でさらに厳しくなります。こんな社会情勢を背景にして公的資金に依拠する州立大学全般に言えたことは、徴兵逃れの聖域とならないよう成績評価を大変厳しくしていたように思えました。前回述べたように、LSUでも学部生はCを取るのに四苦八苦していました。自国の学生さえ大学に残るのが厳しかったのですから、日本をはじめアジアやアフリカや中近東から殺到する留学生が入学許可を得るのがいかに難しかったかは容易に想像できるでしょう。1970年のアメリカ軍カンボジア侵攻による戦況拡大を匂わせるかのように状況は更に厳しくなっていきました。大学進学率が低くベトナム前線に送られる可能性が高いと見られたアフリカ系アメリカ人の学生組織Black Student Unionの抗議の声も高まり、大学には人種問題も絡んだ反戦の嵐が吹き荒れ始めました。(*6)
一方では声を上げない大多数の“Silent Majority”がおり、その内面を歌うかのように、LSUのキャンパスで観た映画“The Graduate”の主題歌の一つSimon & Garfunkelが歌う”The Sound of Silence”がよく巷に流れていました。
“The Sound of Science Full Album”
筆者は、授業料はなんとか工面できたものの、生活費は底をつき、当時F1ビザの留学生に許されていたオンキャンパスのパートタイム・ワーク(on-campus job)を見つけて働くことになりました。早朝6時から9時までの3時間、学生寮付属のカフェテリアにおける皿洗いの仕事です。女性の総支配人の下に学生パートタイム・ワーカーを監督する学生マネジャーと数名のフルタイム・ワーカーを管轄するフルタイムマネジャーが居ました。学生ワーカーは20名程で、筆者を除き全員白人、フルタイム・ワーカーは4~5名で全員アフリカ系アメリカ人でした。筆者にとっては日常英語を学ぶのには最適な場で、一緒に働いた全員を日常英会話の先生と思いつつ接しました。(*7)
アメリカの大学は午前8時から授業があり、朝食時間開始の7時から皿洗いの現場はまるで戦場です。トレイに乗った食器類がベルトコンベヤーで次から次に送られて来ます。そのコンベヤーに沿って学生アルバイトが並び、並行して設置された勢いよく水が流れるトレイに食べ残しの食料を惜しみなく捨てます。アジア、アフリカ、南米では飢饉が発生し、日本でも戦後の食糧難を乗り越えたばかりの時期でしたから、いとも簡単に食べ物を捨てることには違和感がありました。「トレイの食べ物を食べたり持ち帰ったりしないこと」との警告文を見ながら腑に落ちない気分を持ちながらの作業です。(*8)
列の先頭にアフリカ系アメリカ人のフルタイム・ワーカーが居て送り込まれてくるトレイが溜まるのを上手にさばき、後尾にはもう一人のアフリカ系アメリカ人が積み上げられたトレイと食器を大きな洗浄機に詰め込みます。洗浄されたものを取り上げてさばくのもアフリカ系アメリカ人のフルタイム・ワーカーでした。(*9)基本全員が男。プラスチック製の皿の一片を持ち、こびり付いた食べ物をスチール製の台に叩いて振り落とすけたたましい音が響き渡り、洗浄機の温水で水蒸気が立ち込めていました。”Stop!” “This is ridiculous!” “OK, start again!” “Silverware!” “Stop the dishwashing machine!”など、罵声が飛び交うのです。何をstopし、何をstartするのか、何がridiculousなのか、緊迫した現場の状況にあってやっと理解できる会話です。(*10)
“Hey, are you related to Suzuki Motor Cycle?”(*11)隣で作業をする白人学生が冗談半分に質問した一コマを覚えています。”If so,I’m not washing dishes with you!”と言い返したものです。アフリカ系アメリカ人のフルタイム・ワーカーは、初老、中年、20代前半の若者の3人で、白人学生とはあまり口を利きませんでしたが、筆者だけにはよく話しかけてきました。若い方は陽気で、月曜日の朝に顔をあわせると週末行ったパーティーの話をしてくれましたし、白人とアフリカ系アメリカ人のダンスの違いを即興で見せてもくれました。”Hxxxx* dance like this,but Nxxxx* dance like this!”あのシーンは今でも忘れられません!声帯模写と形態模写がとても上手いのです!
そんなある日、いつものように皿洗いの現場に行くと、とても綺麗なアフリカ系アメリカ人女性が居て、筆者の横で作業しはじめました。女性は彼女1人です。彼女は他のアフリカ系アメリカ人とも白人学生とも一言も話さず、以来、いつも筆者の横で作業をすることになりました。夫はUCSBの大学院生らしく、数週間後のある週末、筆者を食事に招いてくれました。夫はアフリカ系アメリカ人で社会学(sociology)を専攻しており、背が高くnice-lookingで、彼女と並ぶと絵に描いたような美男美女カップルです。奨学金だけでは足らず、彼女がパートで働いて生活費の足しにしているとのことでした。
週明けの月曜日の早朝、皿洗いの現場に行くと、どこから漏れたのか、話はアフリカ系アメリカ人の3人の耳に達しており、筆者の顔を見るや大声で”Hey!”と呼びかけてきました。それを機に3人はいろいろなことを筆者に話してくるようになりました。筆者にとってはアフリカ系アメリカ人英語(African American English,略語AAE)と接する最初の場となりました。全部は分からなくてもとても貴重な体験であったことは間違いありません。例の女性は相変わらず筆者の横に立って作業し、筆者も重いものを運ぶときには進んで手を貸してあげました。彼女ともよく話すようになりましたが、彼女はAAEではなくStandard English(SE)で話していたと記憶しています。筆者も彼女もこの皿洗いの現場では特殊な存在であったからでしょうか、互いに親しみを感じ合えたのは確かです。
さて、ハウスメイトのMikeは東洋哲学、わけても、日本の哲学・思想に心酔した白人 (*12)です。菜食主義者で小柄で物静かな青年でした。パンは自分で焼き、床にマットレスを置いて寝ていました。靴を持たず、どこに行くのにも裸足です。当時のヒッピー族と同じように長い髪を後ろで束ね、シャワーがあるのにあまり入りませんでした。人付き合いはあまり無く、唯一の友人と言えば前述したあのTomだけでした。そのTomも同じアパートに住んでおり、頻繁に筆者らの部屋に来ては話し込みました。長距離歩行ができないので1955年製の古いアメリカ車を足代わりにしていました。マフラーからは多量の煙を放出しガソリンを入れる度にオイルを補充していたのが印象的です。車を持たない筆者とMikeもあちこち連れて行ってもらいました。
筆者らの部屋は一階で、Tomはアフリカ系アメリカ人のルームメイトのRufusと二階に住んでいました。Rufusは大学3年であったと記憶していますが、とても綺麗好きで、彼らの部屋のリビング、キッチン、ベッドルームとも綺麗にきちんと整頓され、筆者らの部屋とは大違いでした。Rufusはアパートの大家さんに信頼され、アパート全体の管理を任され、時々大家さんが訪ねて来て管理上の話をしていました。Rufusも物静かで控えめな青年でしたが話すとなかなか饒舌で、授業外で現地学生と話すとても良い機会になりました。

(筆者が住んでいたアパートはそのまま残っていた。1995年頃)
大学のキャンパスは、筆者のアパートから歩いて10分くらいの所にありました。朝5時半に起きてキャンパスに行き、6時から8時までカフェテリアで働いてそのまま授業を受け、午後遅くから図書館で勉強というのが筆者の週日の生活パターンです。授業に話を移すと、9月末に新入り留学生7名全員が英語のテストを受けるよう言われました。その後に行った大学でもそうでした。全員半ば強制的にEFL(English as a Foreign Language)のコースを受けることになり、その為に履修できる英文学の授業はたった一つということになったのです。それも、UCSBに在籍したFall QuarterとWinter Quarterの2学期に亘り履修させられました。しかも、EFLコースは一つしか設置されておらず、全員がそこに押し込められたことで低いレベルの履修者に合わせざるを得ず、筆者にはあまりにも易しすぎました。アメリカの大学は嘆願書(petition letter)を書けば考慮されることを薄々知っていましたが、そのまま履修し続けてしまったのが今でも心残りです。(*13)
英文学の授業はとても充実していました。Fall QuarterとWinter Quarterに履修した2つの授業で、17世紀(The Seventeenth Century)後半、18世紀(The Restoration and the Eighteenth Century)、19世紀(The Victorian Age)における主要小説(novels)を読みました。授業は月、水、金の午前中で、毎授業1作品を扱い、冒頭でquizがあり、その後はdiscussion形式で進められます。
学生は15名程、全員が手を上げて活発な意見を述べ、ただただ圧倒されるばかりでした。早口で間髪入れず飛び交う議論についていけません。それでも、クラスメートの中に高校のEnglish(英文学)を教える免状(teaching credential)を取りたいという30代の女性がおり、授業後にカフェテリアで頻繁に話すようになりました。
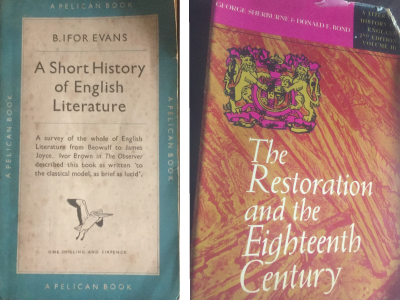 (Evan’s小英文学史) (王政復古&18世紀文学)
(Evan’s小英文学史) (王政復古&18世紀文学)
彼女はこの授業を含めて4つ履修しており、週に10作品以上を読まなければならないとのこと。(*14)単純に計算すると1時間80ページ近く読まなければついていけません。1冊を1年かけて、しかも訳読で終わる日本の英文学科の授業は一体何だったのでしょうか。ここでは、毎回quizをされてdiscussionし、2ヶ月半のQuarterの間に、mid-term examinationとfinal examination、プラス、mid-term paperとfinal paperを書いて出さなければならないのです。そんな授業を4つも取っているなどこの時点の筆者には想像さえできませんでした。(*15)
Quarter制度はとても忙しく、始まって3、4週間でmid-term paperを提出しなければなりません。筆者はSwiftのGulliver’s Travelsのsatiresを取り上げました。この作品は全4篇から成る長編で、読むのに1週間、書くのに1週間、合計2週間もかけてやっと書き上げました。ここで情けない問題に直面しました。アメリカの大学では手書き(hand-written)のpaperを原則受け取りません。当時の筆者はタイプが打てず、高価なタイプライターも無く、先生に嘆願しhand-writtenで許してもらいました。先生の名前を忘れてしまいましたが、30代後半のassociate professor(助教授)で、クラスdiscussionについていけない筆者を怒ることもなく、ゆっくり優しく質問し発言を促してくれたことを覚えています。
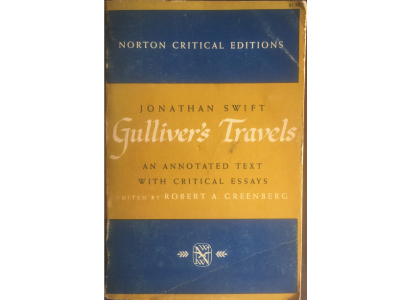 (Gulliver’s Travels)
(Gulliver’s Travels)
血の滲むような思いでpaperを書き終えて提出すると次はmid-term examに備えて猛勉強です。もう一度読んだ全作品に目を通しました。毎晩5時間、6時間勉強してやっと追いつくかどうかの膨大な量です。ある日、授業に5分ほど遅れてしまいました。先生とクラスメートが全員筆者の顔を見ています。すると先生が筆者にpaperを渡しました。見るとB+と付いていました。”Mr.Suzuki,this is an excellent paper.”とのコメント付きです。兎にも角にもアメリカ人と競争してB以上取れたことにホッとしました。授業が終わり何時ものようにカフェテリアに行くと、例のクラスメートが筆者を待っていました。開口一番、”You know what?Before you came in the classroom,Mr.~said that a foreign student, which is you,wrote the best paper.”と言いました。これで筆者が遅れて入っていった時にクラス全員が筆者の顔を見たわけが分かりました。”Oh,yeah.”筆者はクールを装い返事をしましたが、内心は飛び上がる程嬉しかったのを覚えています。
喜んでばかりはいられません。その後のmid-term examinationが心配です。指定された作品を読んだのち、時間をかけて書き上げることのできるpaperと違い、試験は2問ほどの質問に対してその場でエッセイを書かなければなりません。当時のアメリカの大学、大学院ではblue bookという試験解答用の小冊子を使っていました。English majorに求められるessay writingですから、当然、Englishの質も問われます。「火事場の馬鹿力」とはよく言ったものです。筆者もblue bookにびっしりエッセイを書いて提出しました。翌週返却された成績は確かB+でした。何年先になるかはしれないが、このまま努力を続ければPh.D.が取れるだろうという淡い感触を得て長期滞在することを決めたのでした。
担当の先生の名前を失念してしまいましたが、アメリカ人にしては小柄で、ジャケットにネクタイを締め、やや赤毛で端正な口髭とアゴ髭を蓄え、身なりのきちんとした紳士でした。ソフト・スポークンで穏やかな性格で、当時は珍しかった日本からの留学生の筆者にとても親切に接してくれました。綺麗な英語でゆっくり分かり易く、学生の意見を誘発してくれ、こんな先生に早くから手ほどきを受けていたら、もっと英文学が好きになっていただろうと思いました。しかし、授業は厳しく、時間通りに始まり、時間通りに終わり、シラバスにある全作品をカバーし、一度でも授業を欠席したら大変なことになります。こうして12月中旬にfinal paperを書いて提出し、その後、final examinationを受けてWinter Quarterは終わりました。筆者の両方の成績はB+でしたが、UCSBのfinal gradeにはB+という表記はないのでB。とは言えクラスの平均成績はCと聞いたので、初回としてはまあまあでした。
12月下旬から1月初旬まではWinter Breakで、学生は家族とChristmasを祝うために親元に帰り、Goletaの街からは人影が消えます。筆者は、この間に親しくなった日系三世の学部4年生の誘いで、Fresno市近郊にある彼の両親が所有するぶどう園に行ってChristmasを過ごしました。40acres(約49,000坪)の農園はブドウ園としては小規模ということでしたが、そこで帰米二世で日本語と英語を話すご両親と、英語しか話せない妹さんと彼の4人で暮らしていました。Fresno市は内陸部の中堅都市、農業、牧畜が盛んな盆地で夏はとても暑いので有名です。しかし、冬は朝晩零下まで気温が下がり、乾いた大地に散らばる家々の屋根の軒先に光るChristmasのライトが晴れて澄み切った夜空を飾っていました。
UCSBには彼以外に多くの日系三世の学生がおり教員や医者を目指していました。彼も医者を目指しており、本コラム第95回「アメリカの医学部(medical school)に入学するには」でも紹介したpre-medコースを取っていました。(*16)中古のMGAのスポーツカーを持っており、滞在中の2日間を利用し、San FranciscoのUniversity of California San Francisco Medical Center(*17)の下見に同行しました。San Franciscoに着くと、UC Berkeleyの学生で同じくpre-medを取っている彼の三世の友人と落ち合い、有名なロックハウスFilmore Westで生ロックを聴き、Bay Bridge経由で対岸のBerkeleyに行ってパブに入り、即興で作った詩を吟じ合う様子を見て浮かれ、非常に濃い2日間を過ごしました。(*18)この体験がSan Francisco Bay Areaへの関心を高めてくれました。
年明けの1969年1月の2週目にWinter Quarterが始まりました。3月中旬過ぎまでの2ヶ月半です。相変わらず、指定されたEFLの授業からは解放されず、前学期の続きの英文学の授業に全精力を傾けました。12月末あたりからCalifornia州は雨季に入ります。Albert Hammondの”It never rains in southern California“という曲に、”Seems it never rains in Southern California……but it pours,man,it pours”というサビがあります。隠喩的なくだりですが、南カリフォルニアでは文字通りに雨が降れば篠突く土砂降りなのです。驚きました。それでも人々は傘を持たず、ビニールのゴミ袋に穴を開けてすっぽり被ったり、アルミのトラッシュ・カンの蓋、段ボール、ベニヤ板などを頭の上に翳したりして裸足でペタペタ歩道を歩き廻っていました。滑稽でもあり奇妙でもあるCaliforniaの自由奔放な雰囲気がすっかり気に入ってしまいました。
Winter Quarterの授業は、19世紀The Victorian Age のCharles Dickens(1812-1870)の主要作品を中心に、William Makepeace Thackeray(1811-1863)やGeorge Eliot(1819-1880)などの作品をカバーしたと記憶しています。先生は40歳前後の、ラフな格好をした男性で、シニカルでシャイな笑みを浮かべながらボソボソと呟くように話す小説家タイプの先生でした。2月のある日サンタバーバラ地方で大洪水が発生し洪水に見舞われた時のこと、水に埋まった自宅のアパートを途方に暮れながら眺める先生の姿が地元テレビ局のニュースで放映されました。その数日後の授業中のことです。また雨が激しく降り始めると、discussionもそぞろに窓の外を恨めしそうに眺める先生を見て、ある男子学生がからかうように言いました。”Mr.~,where did you move this time?”先生はシニカルな微笑で誤魔化すかのようにdiscussionへ戻りました。あの表情が未だに忘れられません。DickensのGreat Expectationsの主人公Pipの義兄にシャイで人柄が良いJoeがいますが、筆者にこのJoeを連想させる先生でした。(*19)
筆者はこの授業のpaperでDickensのA Tale of Two Citiesを取り上げ、(*20)同じくB+を貰い、ますます英文学が好きになりました。UCSBで履修した2つの英文学のコースは、アメリカの大学の英米文学科のレベルの高さを認識させ、挑戦しようという意欲を高めてくれる授業でした。残念ながら二人の先生の名前を覚えていません。
UCSBは文学だけではなく環境問題への意識を高めてくれました。筆者が滞在中、沖合の海底油田に事故が起き、UCSBのビーチは油で真っ黒になり、海鳥はタールにまみれて死ぬ寸前の姿であちこちに横たわっていました。それを見たUCSBの学生たちはそれらの海鳥をなんとか蘇生させようとタールを洗い落とそうと懸命になっていました。地球は人間だけのものではないことを訴えた出来事です。2011年東日本大震災で東京電力福島原発爆発事故が発生し、放射能汚染地域に動物たちが取り残されてしまいましたが、2つは重なります。
“The 1969 Santa Barbara oil spills that changed gas and oil exploration forever”
前回でも述べた通り、渡米して半年足らず、アメリカの大学の正規の授業を受けたことがない筆者にとって、UCSBはその後10年続くことになるアメリカ留学生活への良きgateway(玄関口)でした。この6ヶ月間に会った先生、友人、そしてアルバイトの仲間全ての人が、アメリカの大学コミュニティーへの良きオリエンテーションをしてくれました。筆者にとっては全員がmemorable teachersなのです。
UCSBの学生の多くは、卒業後、アメリカ各地のトップ大学院に進学し、とても優秀で一緒に勉強し、生活した学生からも多くのことを学びました。その一人が冒頭に挙げたTomです。Tomはアメリカの大学院のEnglish programsについて色々教えてくれました。確か、creative writingを学び、short storiesのwriterになりたいと言っていたように記憶しています。Sherwood Anderson(*21)のWinesburg, Ohioについて話しが盛り上がりました。2月のある週末、Los Angelesのhost familyの家に行くというので同行しました。上述した「ソーエンソン」の家です。場所は忘れましたが、中年のご婦人が出てきてTomを見るなり熱く抱擁しました。決して裕福ではない家の中には数人のアジア系の子供達が居て、Tomと筆者を大歓迎してくれました。皆大事に育てられている様子が見て取れ、アメリカ人の懐の深さを教えらました。一緒に囲んだ食卓での団欒からTomが文学に関心を持ったのはご婦人の影響があったのではと感じました。
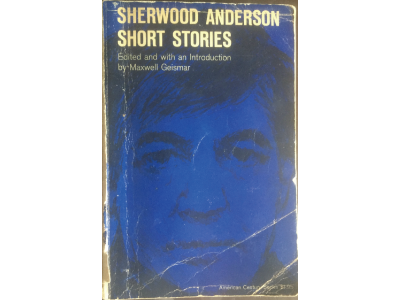 (Sherwood. Anderson Short Stories)
(Sherwood. Anderson Short Stories)
3月末にWinter Quarterが終了した時点で、University of California systemの1quarter$500のout-of-state tuitionを賄えないことが決定的になりましたが、(*22)California State College systemの大学院であればその10分の1程度になることを知り、Spring Quarterに向けてSan Francisco湾の東側にあるCalifornia State College at Hayward(現California State University, East Bay)へと旅立ちました。(*23)映画”The Graduate”の最後の教会のシーンと二人でバスに乗り込んで逃げるシーンのロケ地となった街並みを見ながら6ヶ月世話になったGoletaに別れを告げました。筆者10年間の留学中UCSB時代のみ写真は一枚もありません。写真を撮る余裕がなかったのです。心象を頼りに記憶を手繰り寄せながら本稿を書きましたが、そのことが返って懐かしさを醸造してくれたような気もします。続きは別稿で。
(2019年10月23日記)
(*1)California州にはスペイン語の地名が多く、スペイン語訛りと英語訛りの発音の仕方があります。Goletaはスペイン語訛りでは/go le ta/英語訛りでは/go li: ta/と発音されますが、筆者は後者をよく耳にしたと記憶しています。前者と後者の中間の発音もあるようです。スペイン語に由来する地名は英語話者にも難しいようで、この点だけでも、アメリカ英語の発音は一筋縄では行きません。興味がある読者は、次のサイトを参照してください。”California City Names Pronunciation“
(*2)当時はアメリカの多くの大学のキャンパスにはInternational House(略称I House)という宿舎がありました。大学により名称は異なりますが、当時のUCSBにもI Houseがあったと記憶しています。
(*3)以前にも話しましたが、アメリカでは卒業する大学の大学院にそのまま進まず、他大学の大学院に進むというケースの方が圧倒的に多いです。1970年代のUC Berkeley(UCB)の大学院カタログには、UCB卒の学生がそのままUCBの大学院に行く事を奨励しないとさえ書いてありました。TomもUCSBの大学院ではなく他の大学院を狙っていました。但し、scholarshipかfellowshipをくれることが条件で、その返事待ちだと言っていました。
(*4)アメリカの大学と交換留学協定を結んでいた大学からの交換学生は比較的スムーズに英米文学科に受け入れられていました。但し、原則1年在籍して日本に帰らなければならなかったようです。日本の大学に帰らずそのまま在籍して卒業する人は稀少でした。
(*5)”Over the Waves”(1884年)はメキシコ人作曲家によるワルツです。世界中で流行し、日本にも「波濤を超えて」と邦訳されて入ってきました。筆者はGeorge Lewis楽団が演じるバージョンが好きです。最初はBlues調にもの悲しげにゆっくりと、後半は速いテンポで軽快に演奏しています。留学中はこの曲をよく口ずさみました。遅々として進まぬ前半の4年間、一気に進み出した後半の6年間が重なりました。ちなみに、New Orleansの伝統的な葬式の行列では、列を導くmarching bandが、往きはスローテンポでゆっくり演奏し、故人を悲しみ静かに行進します。一転、埋葬を終えるや、故人が天国に行ったことを喜んでアップテンポに演奏しながら賑やかに帰ります。そのGeorge Lewisは1968年12月31日にNew Orleansに亡くなり、彼の葬式の模様がテレビのニュースで流れました。New Orleans最後の伝統に則ったものになるかもしれないと述べていました。
(*6)University of California,Berkeleyは当時反戦運動の中心で、California州知事(後大統領)Ronald Reaganは反戦活動家の一掃を図る為にUniversity of California System全体の授業料を上げたとも言われました。その後、1970年5月4日Ohio州Kent State UniversityではThe Ohio National Guardが反戦デモの学生に発砲したのをきっかけに全米の大学で学生による授業放棄のストライキが始まりました。以下の関連記事など参照してください。 “Berkeley, A History of Disobedience in Pictures” “The Invasion of Cambodia” “Kent State Shooting” UCSBのBlack Student Unionが校舎を占拠した事件は全米の注目を浴び、筆者自身、学生たちが賛否両論の激論を交わしている現場を見ました。1968″A Global Year of Student Driven Change“
(*7)筆者は1967年にお茶の水駅近くの英会話学校に通ったことがあります。講師はUC Berkeleyでsociologyの大学院に応募していて返事待ちのアメリカ人の男性でした。とても良い人でしたが、何せ料金が高くて回数が限られた為、あまり上達しませんでした。それに比べたら、お金を貰いながら毎日3時間もnative speakersと話せるのですからとても価値ある体験でした。アメリカのon-campus jobsはこうした肉体労働だけではなく、図書館、各種officesでの仕事、大学院生には教える仕事もありました。仕事を通して学ぶ、これもアメリカpragmatismの影響でしょう。
(*8)現在日本でも賞味期限切れの食べ物を捨てることへの問題意識が高まりつつあります。
(*9)1969年にリリースされた名画”Midnight Cowboy“のオープニング・シーンではテキサス州のある街のカフェテリアの皿洗いの現場が出てきます。筆者が働いたUCSBのカフェテリアはもっと綺麗でしたが、主役Joe Buck(Joh Voight)と現場監督African Americanとのやりとりなど、この映画を見るたびに懐かしさが込み上げてきます。ちなみに、Harry Nilssonの歌う主題歌”Everybody’s talking at me“は世界中で大ヒットしました。
(*10)筆者は後になり言語使用における状況の意味を究明してきました。UCSBでの皿洗いの現場はその良例です。ここでは主語や目的は言語化されず、状況から判断しなければなりません。言語教育にも応用できます。これらに関する拙著書、論文、英語教科書については本コラムのバックナンバーの稿にあります。「バックナンバーの記事はこちら」
(*11)1968年、まだ、California州でさえ日本の自動車を見かけることは稀でした。輸入車といえば、VW Beetleの全盛期でしたが、オートバイはSuzuki, Honda, Kawasakiなどをよく見かけました。お陰で筆者の苗字Suzukiはすぐ覚えてもらえました。
(*12)正式には、白人はCaucasians(コーカサス人)、黒人はAfrican Americans、アジア人はAsian Americans、アメリカ・インディアンはNative Americansであることも分かってきました。東洋人orientalとかnegroという呼称は前時代的なものとして避けられ、Mexican Americans,Japanese Americans, Chinese Americans, Italian Americans, Polish Americans, Jewish Americansなど出身民族や国別呼称も使われて始めました。所謂白人の中には、”I’m half French and half Irish.”とか”I’m one quarter of Swedish.”などという言い方をよく耳にしました。自分のルーツを探りそれを誇りにするという考え方が根付きはじめた時期です。
(*13)アメリカでは学業に関することで迷ったらアカデミック・アドバイザーに相談し、嘆願書を書くと認められることがあります。以前、EFLは最初の数ヶ月取れば十分であること、なるべく早く正規の授業を取ることなどを述べましたが、全てUCSBでの経験に基づいたものです。
(*14)巷間、英語は聞くだけで話せるなどという宣伝文句が飛び交っていますが、簡単な会話に限って言えばそうかもしれませんが、高度のdiscussionになるとそうはいきません。母語でも日常会話はできても高度の議論・討論ができるとは限りません。
(*15)古典から現代までの全ジャンルの主要作品の数は膨大で学部卒業までに読まなければならず、各授業膨大量のreadingが要求されました。渡米直後の筆者はお手上げでしたが、その後2、3年もすると慣れました。
(*16)第95回「アメリカの医学部(medical school)に入学するには」はこの時の体験もベースになっています。彼とその友達からmedical schoolsに入るのがいかに難しいかがよく分かりました。
(*17) University of California San Francisco Medical Center。山中伸弥博士もここで研究されていました。
(*18)これらは映画”The Graduate”の馴染みのシーンです。
(*19) “Great Expectation Novel by Charles Dickens”Encyclopedia Britannicaを参照してください。ネット上に作品のPDF版もありますから読んでみましょう。
(*20)A Tale of Two Cities Novel by Charles Dickens PDF Planet eBoook
(*21)”Sherwood Anderson| American Author|Britanica.com“Andersonの作品は、翻訳されていますが、原書で読んでみましょう。
(*22)年間では$1,500になりました。当時1$は360円、日本の平均年収は360,000円($1,000)前後で、とても賄える額ではありませんでした。
(*23)California State College(現University)にgraduate studentとして受け入れてもらいました。California State Collegeはどの専攻でも修士課程しかなく、また、同専攻同学位を取れないという規定もあり、学位を取らないという意味でのnon-objective graduate studentとして受け入れてもらいました。授業料は年間$150、これなら働きながら何とか払えます。昔も今も学費との闘いですね。また別稿でお話しします。

慶應義塾大学名誉教授
Yuji Suzuki, Ph.D.
Professor Emeritus, Keio University
上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏の大学・機関だけでなく、世界160か国、11,500以上の大学・機関で、公式スコアとして留学や就活などに活用されています。コンピュータ上で受験し、スピーキングは回答音声をマイクを通して録音、ライティングはタイピングで回答します。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト
2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場の設定を行うことができます。全国500以上の団体、約22万人以上の方々にご利用いただいています。


Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。