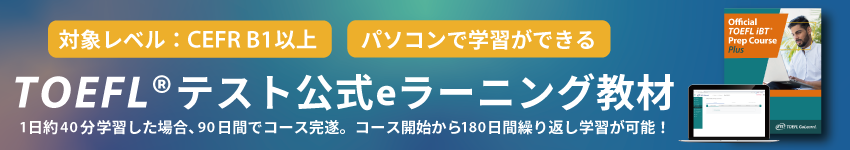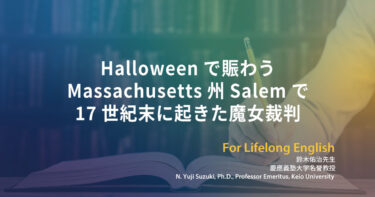第153回の続きです。
恩師Walter A. Cook(1922-1999)先生は、イエズス会シニア・ジェスイット(Senior Jesuit, S.J.)の称号を持つ聖職者で、キャンパス内にある修道院に住んでいました。当時50代半ば、背丈は6 フィート(182cm)越え、がっちりした体格、聖職者が着るキャソック用ズボンにポロシャツ姿です。最近の映画俳優ならNick Nolteに似ています。若い頃はアメリカン・フットボール選手として活躍したとのこと、やや前かがみで颯爽と歩く様はwide receiverを彷彿させるものがありました。フットボール・シーズンになると、“That’s it! Go get’em!”と呟きながら実況中継に見入っていました。
性格はとても淡白で、淡々と端的に意見を述べます。褒めも貶しめもしません。相手が誰であろうと同じです。ある時こんなことがありました。Seminarでのことです。先生がある学術書を取り上げると、聴講生の一人が突如手をあげ、“My book…”と言い始めました。日本のある大学の教員で、普段から誰彼構わず声をかけてあれこれ自慢し迷惑がられていた人物です。先生が“What book?”と聞くと、本人は待ってましたとばかりに自分が日本語訳したD先生の著書のタイトルを言います。先生は“That’s D’s book, not yours. You only translated it.”とバッサリ、容赦ありません。
先生は大学で神学を学びインドで何年か布教活動に従事したようです。Georgetownの大学院で言語学の勉強を始めたのは40才前後、よって、Ph.D.を取得して教職に就いたのは40代半ばの1964年頃であったと思われます。本コラム第145回の後段で Georgetown Universityを紹介する際に述べたとおり、イエズス会は世界各地で布教活動する際、現地語の学習、文字の普及、聖書の翻訳、教育の普及に力を注いだようです。Cook先生もインドでHindu語を学びながらHindu語の文法に関心を持たれたに違いありません。Ph.D. dissertationではHindu語の分析をしたと記憶しています。先生が言語学の勉強を始めた1960年初頭のアメリカ言語学界では、アメリカ構造主義言語学 (American structuralism)の伝統が根強く残る中、Noam Chomskyが提唱した変形成文法(transformational generative linguistics)が隆盛し、それに対抗して生成意味論(generative semantics)、格文法(case grammar)などが出現しました。
言語学は言語の科学的研究です。何をもって「科学」とするか、それにより分析対象・方法論・結果は大きく異なります。上記の言語学理論はいずれも客観科学(objective science)を標榜し、アメリカ構造主義言語学は行動主義心理学(behaviorism)を基盤に、他方、変形生成文法は行動主義心理学を否定するデカルト思想を基盤に言語分析を展開しました。言語は他の能力と同じように刺激と反応の繰り返しで後天的に習得されるとの構造主義言語学の主張に対し、言語はヒトの先天的、生得的能力で自然習得される(innateness hypothesis)とする変形生成文法の主張が真っ向からぶつかりました。[1]
変形生成文法の言語生得説は別の議論を再燃させます。言語生得説は言語の普遍性に依拠する為、言語の相違、すなわち、相対性を主張するSapir-Wharf hypothesis などと対立します。また、言語生得論が言語機能の自律性を主張したのに対して疑義を唱えるH. Putnamらが論戦に加わりました。[2] さらに、変形生成文法では統語論(syntax)を中心としたのに対し、そこから派生した生成意味論は意味論(semantics)を中心としてぶつかりました。まさに混沌とした巴戦でした。
言語は多岐の分野に関わるので、言語研究への新規参入は続き、1960年代から1970年代の言語学界は大変な活況を呈し、言語学修士課程や博士課程は多くの学生を集めていました。あちこちで開かれた学術学会では活発な論戦が繰り広げられ、それが嵩じて激しいなじり合いになったこともあります。そうした風潮を裏付けるかのように、当時出版された学術論文の中には皮肉と諧謔に満ちたものが多々ありました。いかなる理論もそれだけが独立して突如生まれることはありません。様々な考えの上に成り立っているのです。Umberto EcoはSaussureの記号論でさえ、Saussureが単独に考えついたものではなく、過去を遡ればその根本となる考え方があり、その影響を受けて辿り着いたものであると述べています。
Cook先生が言語学を勉強し始めた頃は、言語学界が出入りの激しい過渡期であったこと、また、ご自身40歳前後であったことから、数ある言語理論がそれぞれどのような方法論でどのような分析をしているかその骨子を冷静に学ぼうとしたものと推察します。そうした上でそれぞれを比較し、互いの関連性を見出し、一つの有機体としての言語理論を描こうとしていたのではないかと。先生の著書論文そして授業から学んだことを基に筆者の知る限りで想像してみると、最初に手がけたのはアメリカ構造主義言語学とはやや趣を異にし、言語形態の持つ機能を重視するKenneth L. Pikeが提唱したtagmemics という文法理論で、[3] 先生のPh.D. dissertationはtagmemicsによるHindu語の分析であったように聞いています。後にIntroduction to Tagmemic Analysis (Walter A. Cook. Holt, Rinehart and Winston. Inc., 1969)に纏めています。[4] その後は、変形生成文法の起点となったNoam ChomskyのSyntactic Structures (Mouton, 1957) そしてその原典Aspects of the Theory of Syntax (MIT Press, 1965)、Charles Fillmoreの格文法(case grammar)の原典The Case for Case (Charles Fillmore, 1968)、格文法や生成意味論の繋ぎ役的なWallace ChafeのMeaning and the Structure of Language (The University of Chicago Press,1970)、生成意味論の旗頭George Lakoff、James McCawley、John Ross, Paul Postalらが1960年代後半から1970年代前半に書いた全主要論文などの骨子をまとめ、Seminarで一つ一つ入念に検証しながら授業を進めました。筆者ら学生も英語やそれぞれの母語、第一外国語から例を提供し討論しました。
これに関し、面白い話をクラスメートのSteve M.君から聞きました。M君は1973年筆者と一緒にPh.D. courseを始め、当時は珍しく、学部でも言語学を専攻した人で、あちこちの大学に言語学専攻の友人がおり、ある時MITの友人にあった時のことです。ご存知のようにChomskyはMITで教鞭をとっており、MITの言語学科と言えば、変形生成文法の聖地のような存在でした。言語学コースはそれに特化し、学部、大学院コースではChomskyを筆頭に彼の理論を継承する若手の錚々たる精鋭が担当していたことでしょう。M君がその友達にMITでの授業内容を聞いた際、彼が取り出したゼロックスコピーを見て驚きました。なんとそれは上記の写真にある、Cook先生が、担当するtransformational grammar導入コース用に纏め、学生に配布したSyntactic StructuresとAspectsのコピーでした。Cook先生が諸理論の原点とも言える著書、論文の骨子を纏めた資料の質の高さを物語っています。
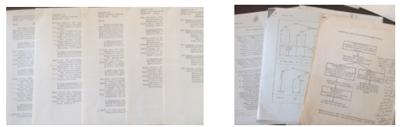
Cook先生のSeminar(Spring,1975)でカーバーした論文リスト Cook先生作成のChomsky (1965)の骨子の冊子
先生は上記の理論だけではなく、アメリカ構造主義言語学が非科学的な分析として切り捨てた伝統文法(traditional grammar)について、“Any serious study of language should refer to Jespersen.”と述べ、Otto Jespersen のModern English Grammar on Historical Principles (George Allen and Unwin, LTD, 1931)を読むよう勧められました。また、本コラムで何度も紹介している言語哲学のJ. L. Austin、John Searle、Paul Griceなどの著書、論文を含め、多くの著書、論文を読むよう推奨しました。要は、まず、何の理論的偏見も入れずに言語学界で過去から現在までに出版された主要研究を理解する、その上でそれらの関連性を見出し、集めた言語データを最も的確に分析しうる理論(複数理論の折衷かもしれません)を見つけるよう学生に勧めたのです。よって、第149回で述べた分析方法論としては、演繹法(deductive reasoning)ではなく、帰納法 (inductive reasoning) を推奨しました。
当時の言語学界は“given that…”(〜とすれば)を前提に数々の議論が繰り広げられました。ChomskyはAspectsで、「理想的話者・聞き手」“the ideal speaker-hearer”の言語の分析を大前提にしていますが、これこそ“given that…”です。対する生成意味論者らも“given that…”で応戦しました。どちらも現実の言語データから乖離し、ドッグファイトの様相を呈してきました。演繹法が陥りやすい誤りです。[5] 言語は数学・論理のように客体化できる対象ではなく、種々雑多な言語社会の種々雑多な話者が生成するdiversity現象で、そうした方法論にはなじみません。その後、生成意味論の提唱者の一人G. Lakoffは、相対的な言語現象に目を向けています。[6] Cook先生は英語の動詞、法助動詞、相、形容詞などのデータを集めて著書、論文を書かれています。Seminarでの討論もinductiveでしたから、必然的にそれぞれの理論の強さ、欠点、類似性や繋がりがよく分かりました。「それJespersenが言ったことじゃないか」とか「この理論はここを端折ったな、ではこうすればよくないか」とか言い合いながらの討論は本当に楽しかったです。
前回述べたように、筆者がPh.D. dissertationを提出し、defenseを済ませ、無事博士号(Ph.D.)を修得したのは1978年2月で、それまでは授業や研究室以外にCook先生と話す機会はありませんでした。その後、慶應義塾大学経済学部で英語の専任教員となり約10年経た1990年に湘南藤沢キャンパスに移籍しました。同年3月に開催されたGeorgetown University Round Table On Languages and Linguistics 1990: Linguistics, Language Teaching and Language Acquisition: The Independence of Theory, Practice and Researchに招待され、筆者は
“A Situational Analysis of the Semantics of Can”と称する論文を発表しました。発表時間が30分と限られていたので、法助動詞で意味論的に最も複雑なcanに絞ったshort versionです。壇上で筆者を紹介してくれたのはCook先生でした。先生の前で卒業後10年の法助動詞の研究成果を発表できたことは生涯の思い出です。発表後は先生のご招待で会場となったThe Georgetown Hotel and Conference CenterのレストランでSeminar後輩も交えて夕食を共にしながら歓談しました。

1990年3月Cook先生、後輩と
その後、Cook先生は日本に何度か来られました。上智大学にはGeorgetown時代の同級生で、同じくS.J.で同大学外国語学部スペイン語学科教授のLobo先生(S.J.)達に会う為でした。上智大学は同じくイエズス会系の大学で、その修道院に宿泊されていました。先生はいらっしゃるたびに連絡をくださり、上智大学の近くのレストランで会食をしました。アメリカの大学では定年がありませんが先生は1992年70才なると引退されました。元気な先生ですが流石疲れたそうです。それはそうでしょう。先生は上述したように絶えずデータを集め、手を抜くことなく学生と共に分析しつつ、思索に明け暮れていたのですから。先生は小さなグループでの討論が好きでしたから、それはそれで一人一人の意見を聞いて考えを述べなければならず、授業後は相当疲れたものと想像できます。
先生は茶目っ気たっぷりで、三つ子の魂百までを地でいくエピソードもたっぷりです。筆者と食事をしている時、野菜が大嫌いな先生はゆっくり肉料理を食べながら、“Oh, how I hate vegetables!”と言い、グリンピース、トマト、レタスなどの付け合わせ野菜は横に押し退けてしまいました。 “But they are good for your health, Father.”と筆者、“Not for me.”とCook先生。悪いことにはデザートに出てきたのは抹茶アイスクリームでした。案の定“Yuck! Green-tea ice cream? You eat it for me.”と言いました。抹茶アイスクリーム出始めの頃で、今でこそ国内外で好まれていますが、当時は日本人の中にも好き嫌いがありました。抹茶があれば紅茶アイスクリームなるものがあってもおかしくありませんが、先生は同じように“Yuck!”と言ったことでしょう。多分少年時代も大の野菜嫌いだったでしょう。その瞬間の Cook先生はCook少年でした。当時小学生と中学生の息子を抱えていた筆者は、つい彼らに言うような言い方をしてしまったものです。
最後にCook先生にお目にかかったのは1996年7月のことでした。筆者は湘南藤沢キャンパスの同僚の田中茂範氏と共同で、学内外の言語学や自然言語処理の専門家ら10名程度に声を掛け、上智大学に滞在中のCook先生を講師として招待し、格文法(case grammar)の講義をしていただいたのです。先生は筆者が卒業後自然言語処理に関心を持たれ、格文法を自然言語処理に応用する方法論を思索し、Case Grammar Applied を出版されていました。1996年は筆者自身同キャンパス政策メディア研究科でプロジェクト科目(Cognition, Action and Media in Language and Language Education CAMILLE)を担当していたので大いに関心があるテーマでした。かつてのGeorgetownでのSeminarを彷彿されせる内容の濃い講義と出席者による討論が展開されました。

慶應SFC CAMILLE Seminar 講師Cook先生
その後先生とエレベーターに乗ったのですが、それは、筆者がかつてPh.D. dissertationのdefenseが終了した直後の記憶を呼び起こしました。“Yuji.” とCook先生、“Yes, Father.”と筆者、“I’m proud of you.”と先生。先生が人を褒めることは滅多にありませんでしたから、心の中で「え!」と叫びつつ、筆者はなにも言えませんでした。その3年後1999年先生は逝去されました。享年、77才です。1968年から1978年まで続いた長い留学の最後にCook先生のご指導を仰げたことに感謝の念が絶えません。厳しさ、公正、公平、熱心、冷静、暖かさを感じさせてくれた大の恩師です。本当にアメリカに留学してよかったです。(2022年1月5日記)

Commemorating Father Cook, S.J.
[1] “Chomsky vs Skinner: Debate of the Century”などのサイトに論戦の論点があります。
[2] Putnam, Hillary. 1967. ‘The Innateness Hypothesis’ and Explanatory Models in Linguistics” In Synthèse 17. Pragmatism (Blackwell, 1995)に晩年のエッセイがあります。
[3] 筆者はCook先生のTagmemicsと称する授業を取り、1930年代に出たこの理論が、Sapir、アメリカ構造主義言語学(Bloomfield, Friesらの)、変形生成文法(Chomsky)、格文法(Filmore)、生成意味論(Lakoffら)の橋渡し的役割を担っていると感じました。
[4] “JANUALINGUARUM”と称するサイトでも本書が紹介されています。様々な言語の分析に有効な言語理論であることが伺えます。
[5] Chomsky自身“Colorless green sleeps furiously”を例に挙げ、言語( Chomskyのgrammar)における統語論中心説を説きました。意味はナンセンスなのにgrammaticalと主張します。
[6] George Lakoff著書Women, Fire and Dangerous Thingsは、注5のChomskyの文をもじったかのように、一見ナンセンスなタイトルをつけていますが、メタファとしてなら理解できます。その場合、ナンセンスではなく、意味論が重要になります。読者はどう思いますか。Aspectsもこの本も名著です。大学院留学を考えている読者に勧めます。

慶應義塾大学名誉教授
Yuji Suzuki, Ph.D.
Professor Emeritus, Keio University
上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏に限らず、世界の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト
2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場、オンライン受験の設定を行うことができます。


Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。