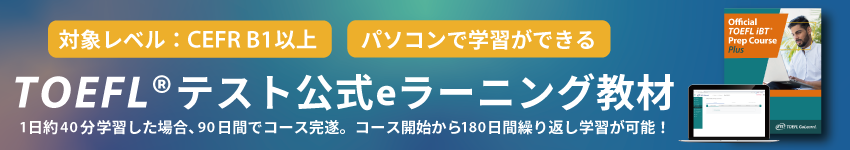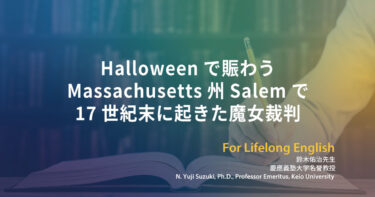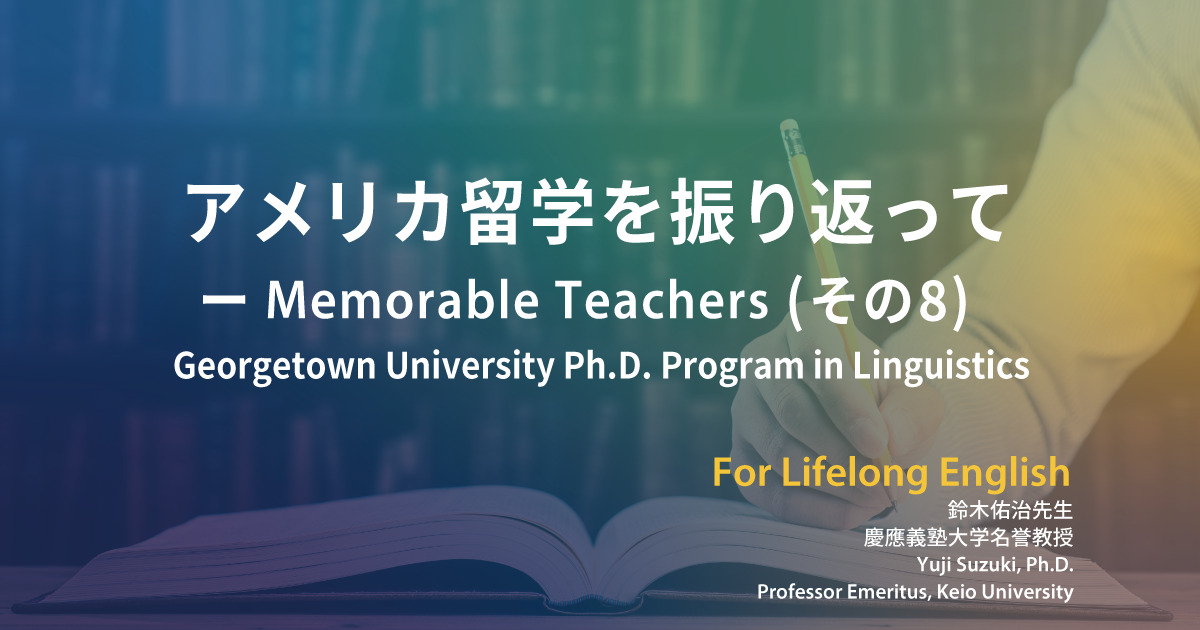
本コラムMemorable Teachersシリーズ(その8)です。シリーズ(その6)の第145回とシリーズ(その7)の第147回では、1973年から1978年まで在籍したGeorgetown University(以降GU)Ph.D. programでの最初の2年、1973年と1974年にお世話になったMemorable Teachersを紹介しました。Ph.D.取得への第一関門のQualifying Examination for Ph.D.に合格し、Ph.D. course workを続行できる許可を得ると、ひたすら授業に集中し、担当する日本語授業ともども、順調に1974年を締めることができました。明けて、1975年の暮れには、第二関門のComprehensive Examination for Ph.D.を受けなければなりません。英語学Ph.D.取得への道が続くか閉ざされるか二つに一つです。精神的にとてもheavyな年でした。受験資格はPh.D. course work(24科目、48単位)の修了をもって発生します。その条件を満たす為、Spring Semesterで最後の4科目、12単位を履修しなければなりません。(*1)英語の法助動詞(modal verbs)をテーマにPh.D. dissertation(博士論文)を書こうと決めていたので、英語の原点を知る必要があると考え、Old English(9454303)を選びました。そして、帰国後英語教育に携わることを念頭に、Language Testing(954310)を選びました。当時GUは社会言語学(sociolinguistics)に力を入れており、Introduction to Sociolinguistics Ⅱ(954364)はa must です。最後に、1974年Fall Semesterに履修したIntroduction to Tagmemic Analysisを担当したWalter A. Cook先生のSeminar-Generative Semantics(95448)を選びました。これら以外にSeminar-Delayed Language Acquisition(954410)を聴講(audit)しました。(*2)
Old English(9454303)は苦戦を強いられた授業です。慶應義塾大学英文学科の原典購読(英語史)でOld Englishに触れてはいたものの、手ほどき程度でした。University of Hawaii(UH)TESLプログラムでのRobert Krohn先生、および、GUでのCharles Kreidler先生のPhonology(音韻論)の授業で、Chomsky and HalleのThe Sound Pattern of English を読んだ際に、the Great Vowel Shift(大母音推移)などOld Englishに関わる知識が必要であることを知りました。また、Ph.D. dissertationのテーマとして考えていた英語法助動詞(modal verbs)のルーツを知る上で不可欠と感じ、選択必須科目として履修することにしたのです。
履修者は筆者を除き学部生のみ、その殆どがドイツ系アメリカ人の2世または3世で、英語・ドイツ語のバイリンガルでした。周知の通り、英語もドイツ語もゲルマン語族(Germanic languages)に属しますが、伝統的構造の多くを失った現代英語に比べ、それを残す現代ドイツ語はOld Englishに類似しています。現代英語からするとOld Englishは死語(dead language)に近く、英語の母語話者にとって外国語同然であり、授業はそのペースで進むものと勝手に思い込んでいました。ところが、小教室はこれらバイリンガルの学部生で独占されていたのです。彼らはいとも簡単にOld Englishの語彙や複雑な活用を覚え、多量の文献も難なく読みこなし、発音も抜群でした。当然、彼らのペースで進み、分厚いテキストと多数のプリントを1学期で終えてしまいました。筆者は、最終成績Aを取れたものの、予習と復習に相当時間を割き、捨て身で望んだ授業でした。
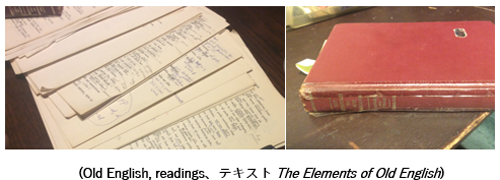
担当は英語学(English linguistics)専攻のHarris先生で、キャンパス近くの英語教育機関にも属していました。60代前半で背が高く端正な顔立ちのsoft-spokenな紳士ですが、厳しく容赦はありません。Old English、Middle English、Modern Englishのスペシャリストで、数ヶ月後のPh.D. Comprehensive Examination for Ph.D.のOral Examination(口頭試験)では手厳しい質問を受けることになります。授業が終わり一息ついた筆者に、“Mr. Suzuki, how are you following the course? So far, you’ve been doing well.”と声を掛けてくれたのを覚えています。
あれから45年経ちますが、Old Englishの知識は、英語学、英語教育の研究に役立ちました。一見かけ離れてはいるものの、現代英語のルーツであることは間違い無く、英語学、英語教育の専攻を考えている読者は一度学んでおくべきです。普段使わないので忘れてしまいますが、教科書、ノートを見れば思い出せます。本コラムで触れた屈折接辞(inflectional affixes)、特にその不規則変化形(go, went, goneなど)、そして、代名詞、法助動詞、冠詞、前置詞、接続詞等々のいわゆる機能語(function words)はみなOld EnglishやMiddle Englishに遡ると言ってよいでしょう。日本語で言えば大和語に当たるもので、中学英語で習う基礎語彙の多くは、例えば、have(=habban)のように、使用頻度(frequency)が高く、バイタリティーがあり、意味、用法が多岐で複雑なものばかりです。関心のある読者は、HEL(History of English Language) on the Webをチェックしてみてください。英語がいかにギリシャ語、ラテン語、フランス語などの影響を受け変化してきたかよく分かります。私たちは古文を何とか読んで理解できますが、英語話者がOld Englishを見ても、同じようには理解できないでしょう。でも、現代英語のルーツはそこにあるのです。
Language Testing(954310)の担当はRobert Lado先生です。Lado先生はアメリカ構造主義言語学(structural linguistics)に基づく言語教育(主として英語教育)を体系化し、英語教育学会では伝説的リーダーの一人です。1975年Spring SemesterにはGUを定年退職されていたと記憶しています。学内にオフィスは無く、Ph.D. dissertationの指導もされず、1975年Spring SemesterにLanguage Testingを、Summer SchoolでTeaching Methodologyの2コースのみ担当されていました。筆者はLanguage Testingの履修をもって必要単位が充足するので、Teaching Methodologyは聴講(audit)することにしました。(*3)先生は、 Linguistic Across Culture、 Language teaching, A Scientific Approach、そして、Language Testingなどの著書を書き、ESLテキストとしては、epoch-makingと称されるEnglish Pattern Practice、そして、Lado English Series Vol.1-を出版しました。WikipediaのRobert Ladoも参照してください。
学生が直接話せる機会は授業中のみでしたが、言語教育への並々ならぬ情熱は言葉の端々に感じられました。言語理論は言語教育から生まれると繰り返し強調していたのが耳に残っています。第二次世界大戦前後の日系社会では帰米2世と称される日系2世がいましたが、先生はスペイン系社会の帰米2世と言えます。スペインで初等・中等教育を受け、21才でアメリカに戻り、大学と大学院に進学しPh.D.を取得しました。自らの子供さんにスペイン語を習わせるなど、スペイン語教育にも熱心でした。言語学の命題の一つに“Language is sound.”があります。従って、言語理論の研究はsoundから始まりsoundで終わります。先生はアメリカ構造主義言語学(structural linguistics)の提唱者の一人で、ことさらsoundに拘りました。言語soundを聞き、繰り返して言語構造パターンを習得する。いわゆるpattern practiceを通しての言語学習です。終始sound中心で文字が入る余地はありません。
ところが、近親に耳の不自由な子供さんがおり、先生は、最初、pattern practiceを通して話す訓練を試みます。効果はあったようですが、健常者のように話せませんでした。そこで思い切ってsoundから文字に切り替えたのです。それが功を奏し、読み書きを通してコミュニケーション力が飛躍的に伸びたとのことでした。以来、先生はreadingとwritingのテキストを多く書かれるようになりました。(*4)先生の言語教育に賭ける熱意が伝わってくるエピソードです。言語教育の現場にこそ的確な言語理論が生まれることを学びました。
1970年代のアメリカ言語学会では、SkinnerやWatsonらの行動主義心理学(behaviorism)に基礎を置く構造主義言語学(structural linguistics)が斜陽になり、変形生成文法(transformational generative grammar、以降TG)が隆盛を極めていました。英語教授法にもその流れが影響し始め、UH TESLのKrohn先生らのEnglish Sentence Structureは、Lado先生のEnglish Pattern PracticeをTG理論に基づき書き換えたものです。それはそれで画期的でしたが、それ以降、TGに基づく画期的な教材・教授法はあまり目にしません。行動主義心理学は、言語を含め知識の習得は刺激(stimulus)と反応(response)による後天的(acquired)学習(learning)を通すとしたのに対し、TGは、ヒトの言語はヒト特有の先天的(innate/built-in)能力で、母語などは簡単な刺激で自然習得される(innateness hypothesis)と主張しました。その是非はともかく、母語ではない外国語学習においては、行動主義が主張する学習理論はそれなりの効果があり、Lado先生が開発した教材、教授法はかなりの影響力を与えてきたと思います。学生への対応は丁寧で、納得するまで忍耐強く質問に応えてくれました。1960年代GU School of Languages and Linguistics(SLL)創設に寄与し、学部長の任につくなど、相当貢献された功労者であることは誰にも明らかでしたが、一切口にすることはありませんでした。先生が逝去された1995年以後いつの間にかSLLは消滅し、College of Arts and Scienceに統合されたと聞き残念に思っています。
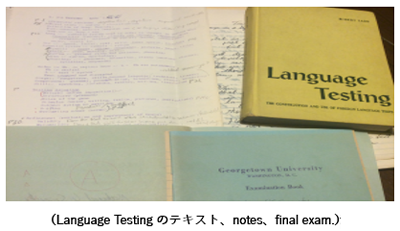
Introduction to Sociolinguistics Ⅱ(954364)は、Personalized System of Instruction(略称PSI)と称するself-studyを取り入れた画期的な授業でした。シラバスの冒頭では、Introduction to SociolinguisticsⅡが後述するIntroduction to Sociolinguistics1と共にPSIによる全米唯一の社会言語学序論であるとの文言が明記されていました。アメリカの大学や大学院の授業は、教員→学生の一方通行の知識伝授型ではなく、教員↔学生の両方向対話型が主流です。両方向対話型授業をPSIでどう実現するのか興味を惹かれました。毎年Fall Semester にIntroduction to Sociolinguistics I(954363)が、Spring SemesterにIntroduction Linguistics Ⅱ(954364)が開講されていました。筆者は1974年Fall SemesterにIを履修できなかったので、1975年Spring SemesterにⅡを取ることになりました。2つとも独立コース(autonomous courses)で、どちらを先に取っても、どちらか1つだけでも問題ありません。Iは言語社会を構成する話者個人(individual speaker)の観点から、Ⅱは言語社会全体の観点から、言語と社会を考察します。例えば、Iでは、話者個人の社会心理的要因によるA言語からB言語への切り替え(code switching)を扱い、Ⅱでは社会全体の政治・社会学的要因によるA言語からB言語への切り替え(language choice)を扱います。テーマが非常にはっきりしていました。
筆者が履修したⅡのコース内容は以下の通りです。テキストはJoshua Fishman編のReadings in the Sociology of Language(1972. Mouton)、Advances in the Sociology of Language Volume Ⅱ(1972. Mouton)とその他社会言語学学術記事です。3topicsの下12 unitsに分け、次の諸項目を網羅しました。
[First Topic: Multilingualism and Nation]Unit 1: Multilingual situations;Unit 2: Diglossia;Unit 3: Qualitative formula;Unit 4: Quantitative formula;Unit 5: Quantitative formula;The numbers that go into and come out of them. [Second Topic: Individual and group Selection of Language] Unit 6: Language attitudes;Unit 7: Language Choice;Unit 8: Language maintenance. [Third Topic: Language Engineering]Unit 9: Language planning and standardization;Unit 10: Language planning cases;Unit 11: The UNESCO Report ;Unit 12: Criticisms of the UNESCO Report.
各unitで、それぞれのテーマに関する複数のreadingsが課せられ、約20の質問項目に答えながら読んで理解したら、指定された日時に教室に行き小テストを受けます。約15問の質問があり正答14個以上パスで次のunitに進みます。但し、*印が付いた最重要の質問を間違えると他が正答でもアウトです。テストはFasold先生のSeminar-Sociolinguisticsに在籍する学生proctorsの一人とman-to-manで実施されます。先生とのin-personで行う全体授業は、最初のorientation、3topicsに関して月1回ペースで行われるclass discussion3回、そして最後のfinal discussionの5回のみです。試験はmid-term examinationとfinal examinationの2つでした。最終評価は12 unitsのテスト50点、mid-term exam. 20点、final exam.30点で合計100点、GU Grading Systemに基づき、A = 95-100、B+=85-94、B= 70-84、C= 50-69、F = 0-49で最終成績が付きます。
PSIは学習者ペース(self-paced)である為に早く進めるも、ゆっくり進めるも履修者次第、早く終える履修者は、semester終了2週間前に実施されるearly final examinationをとることもできます。ゆっくり進めるのも可能ですが、学期終了までに終わらなければ単位は取れません。事前対策として、3回のdiscussion、mid-term examination、final examinationの日程を固定し、更に、12 unitsのテストで得るクレジットを後になるほど多く配分するといったスライド制を採りました。先輩格に当たるproctorsは、この分野の学会誌に論文が掲載されるなど優秀でした。特にアフリカや中南米出身のproctorsからは、アフリカや中南米の多言語社会の実情についての詳細を聞くことができ有意義でした。筆者は、推奨されたスケジュールに沿い、全ての課題や小テストを無事終了しました。達成感が残るとてもよい授業で、最終評価もAでした。

Spring Semester終了後、Fasold先生のOfficeに行き、夏休みにSociolinguistics Iをself-studyしたいのでシラバスをいただけないか尋ねたところ、先生はニコッと笑い、“No.”と答えました。当然です。厚かましく非礼なお願いでした。全units課題をこなしても、あの活発なdiscussion、field work、proctorsとのやりとりが無ければ頭に残りません。その後、筆者は履修した人からシラバスを入手し、夏休みの間に全てのunitsのreadingsを読んで質問に答え、一通りの知識を習得できました。しかし、Sociolinguistics Ⅱの知識と比べ、working knowledgeとしの機能は見劣りします。後に筆者が執筆した社会言語学の論文には、(*5)Ⅱで得た知見が色濃く残り、SociolinguisticsⅡがいかにinteractiveかつproductiveな授業であったか、改めて実感しました。まだpaper-pencilが主流の時代にできたのですから、最近のonline環境をもってすればできない訳がありません。後に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)や立命館大学生命科学部・薬学部で筆者が構築・実践したProject-based English Program(*6)で参考にさせていただきました。Fasold先生はシャイで控えめという印象でしたが、とても精力的でこれら2つのPSI授業を基に2冊の著書を書かれています。The Sociolinguistics of LanguageとThe Sociolinguistics of Societyです。

Seminar-Generative Semantics(95448)は、Walter A. Cook先生担当で、変形生成文法(transformational generative grammar、TG)の対抗理論の一つである生成意味論(generative semantics、以降GS)を追及するseminarです。PartⅠGenerative SemanticsとPartⅡ Modalityに分け、PartⅠではGeorge Lakoff, James McCawley, Robert RossらがTGに対抗しGSを立てるに至った背景・経緯、そして理論そのものを、PartⅡでは、第146回で指摘したように、構造言語学(structural linguistics)もTGも触れてはいるもののあまり取り上げなかったcatenary constructの諸項目、tense、mood、aspect、modal verbs、negativesなどの諸項目に焦点を当て、GS理論やその周辺理論の有効性について考察しました。第146回のmood/modalityについての一考はこの授業で思いついたものです。PartⅠではGS関係の学術論文20点余りと、対抗理論TGの原点と目されたN. Chomsky著Syntax Structuresおよび、Aspects of the Theory of Syntaxを綿密に読みました。先生が授業用に纏めたこれら2冊のChomskyの学術書の要旨は、Chomskyが教鞭をとっていたMITのTGの授業履修者の間に出回っていたと聞き、さもありなんと思いました。また、GSに示唆を与えたJ. L. Austin著How to Do Things with Words、John Searle著Speech Acts、case grammarのCharles Fillmore著The Case for CaseやWallace Chafe著のMeaning of the structure of Languageなど、筆者がPh.D. dissertationで使うことになる学術書・論文を読みました。言語の諸相における意味の関わりを指摘し、軽んじられてきた意味論の中心的な役割とその重要性を説くものばかりです。かつて文学を専攻した筆者には共感できる主張でした。厳しくも充実した授業で、黒板に例題を掲げながら10人程度のクラス全員で議論し、狭い夜の教室には熱気が溢れていました。筆者はCook先生の論文指導の下でPh. D. dissertationを執筆したので、1978年3月にPh.D.を取得するまでこのSeminarに所属することになります。Cook先生については本シリーズ(その9)で詳しく述べます。
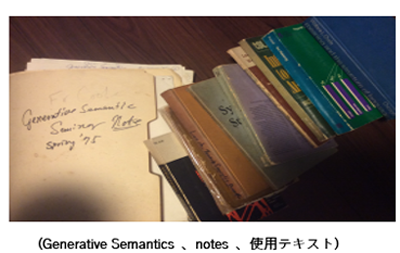
1975年5月1週目にSpring Semesterが終わると、筆者は1年半暮らしたMrs. Higginsの下宿を離れ、GUとAmerican University(AU)の中間にあるapartmentに引っ越しました。GUで週5日午前、AUで週2日午後担当した日本語授業にも慣れ、車も買いあちこち遠出もできるようになりました。ただし、これからはFall Semesterに受けるComprehensive Examination for Ph.D.に向けて猛勉強しなければなりません。5月中ごろから、午前中はGU Summer Schoolの日本語授業を教え、その後は図書館に籠り勉強です。息抜きと言えば、同級生のChris K.君と時々話をするくらいです。Chrisは言語学科master courseの学生で、GU付属のEnglish Language Programで講師もしていました。このプログラムは1年中開講されていましたが、7月下旬から8月初旬に掛けて100名程度の日本人大学生向けの特別プログラムを開講していました。(*7)夜遅く勉強し終えると、Chrisクラスの受講生と筆者の日本語クラスの学生が集まり、団欒の時を持ちました。改めて別稿で述べます。
筆者は1973年にUniversity of Hawaii(UH)TESL MA ProgramでM.A. Comprehensive Examinationを、1974年にGUでQualifying Examination for Ph.D.(Comprehensive Examination for Master of Scienceと併用)を受けましたが、考えてみれば、1968年早稲田大学大学院修士課程ではこれに類する試験はありませんでした。また、筆者が教鞭を執った慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの政策メディア研究科修士課程と博士課程にもこれに類する試験はありませんでした。他大学の大学院については知りませんが、兎に角大変な試験でした。上述のQualifying Examination for Ph.D.は朝から夕方までの1日がかりの試験で、Pass以上のHigh Passで合格するのは難しく猛勉強したことは既に述べた通りです。Comprehensive Examination for Ph.D.はさらに難易度が高い試験で、毎年4月と11月の2回実施され、2日掛りのWritten Preliminary Examinationと、その合格者対象のOral Examinationのセットです。2回受験できますが、2度失敗すると博士課程中途退学で去らなければなりません。
アメリカの大学ではPh.D.が無ければtenure trackの教員にはなれません。Ph.D.を取りtenure trackの助教(assistant professor)に採用されると、数年後にtenure取得審査を受けます。研究・教育・アドミニストレーションの業績による審査で合格すれば准教授(associate professor)昇任、失敗すれば退職です。段階を進むに連れて門は狭くなります。1970年代のアメリカの主要大学では、学部生と同等数の大学院生がおり、また、その先も厳しい審査が待ち構えていることから、Ph.D.コースの段階で容赦無く振り落としたものと推定します。入学許可(admission)を得るのも厳しく、入学後の授業は更に厳しく、これらの試験は輪をかけて厳しかったというのが筆者の印象です。(*8)かくして筆者も学友も神経をすり減らす日々が続き、勉強で疲れても心配で眠れません。体重は10キロ以上も減り、髪の毛も抜け落ちるほどで、精神力と体力による持久戦にもつれ込んで行きました。
手元にあるComprehensive Examination for Ph.D.におけるWritten Preliminary Examinationの1967年から1975年Spring Semesterまでの過去問題があります。(*9)試験準備用に収集したもので断片をつなぎ合わせ復元すると、[Applied Linguistics] Language testing; Methodology; Sociolinguistics/Bilingualism; Psycholinguistics. [Theoretical Linguistics] Grammar; General linguistics; Phonology; Reading list;(*10)Current issues; Historically linguistics; Field methodology.の2セクションで構成され、各1日ずつ2日掛けて行われたと記憶しています。それぞれのセクションには、項目ごと2~3の問題が付され、合計8~12問題が出題され、内5問を選んで答えました。以下、項目ごと1問を選び列記します。
➡️ There has recently been a growing interest in second-language tests for children at the primary school level: relatively few instruments have, however, been produced for subjects at this level. Discuss the problems of the second-language competence of children, indicating the technique you would employ if you were asked to devise such instruments.(Applied: Language test. Spring 1971)
➡️ Discuss the concept of ‘language loyalty’ and its importance in the planning of social programs.(Applied: Sociolinguistic/Bilingualism, Spring 1971)
➡️ What are Chomsky’s objection to the concepts of verbal learning and behavior developed by B.F. Skinner? Discuss.(Applied: Psycholinguistics, Spring1971)
➡️ Describe some of the ways in which linguists have evaluated the adequacy of grammar. How inclusively descriptive of human language should a grammar be of?(Theoretical: Grammar, Fall 1973)
➡️ If you were called upon to create an artificial language to be used for communication across natural language boundaries, what features of natural language would you include and which would you exclude. Justify. (Theoretical: General linguistics, Fall 1973)
➡️ Summarize and critique Lenneberg’s thesis(The Biological Foundation of Language)that language is natural to men as opposed to the view that language is an overlaid function(as in Sapir’s Language)? (Theoretical: Reading list, Fall1973)
➡️ How does one check the reliability of an informant? Are there alternative approaches to field methods which do not involve direct work with one or two informants?(Theoretical: Field methodology, Fall 1973)
➡️ Is phonological analysis in any way dependent on phonetic data? Which phonological analysis is more phonetically based, in your opinion? (Theoretical: Phonology. Fall 1973)
➡️ What problems for linguistic analysis arise from considering idioms and metaphors? Evaluate Chafe’s and Hockett’s approach to idioms and/or present approach of your own.(Theoretical: Current issues. Fall 1973)
➡️ Discuss the contribution to the study of language change which derives from taking into account variation in social structures.(Theoretical: Historical linguistics. Fall 1971)
実際の出題数はこの3倍強、全部読んで選択するまでに1時間半余が掛かります。そしてコーヒー・ブレイクを取った後、1問ずつ構想を練って書き始めます。1問終えると、コーヒー・ブレイクでまた1問、こう繰り返すうちに高揚し、やがて楽しむ余裕さえ生まれ、何時間でも続けられそうな気がしたものです。それでも、2日目も終わりに近づくにつれて右手が痺れて力が入らなくなり、肉体的限界を感じました。(*11)Thanks Giving Holidayを挟み、12月初旬にWritten Preliminary Examinationの合否発表がありました。SLLのベテラン秘書から電話があり、“Mr. Suzuki?” “Yes.” “This is Mrs._ from Deans’ Office. Congratulations! You’ve passed!”と言うや電話が切れました。それから数日後にComprehensive Examination for Ph.D.におけるOral Examinationに臨みましたが、これが又厳しい。厳かなSLL応接室に通され、円卓テーブルの反対側には5名の先生方の姿がありました。始まるや矢継ぎ早に投げかけられる質問の数々、怯まずに応えることができました。今でも夢に見るシーンは、英語学者Harris先生のテレビ番組で使用される英語についての質問に咄嗟には答えられず一瞬戸惑ってしまったことです。次の瞬間、もう一人の英語学者Macdonald先生が別角度から問い直してくれ、我に返り、答えることができました。終了すると一旦部屋の外に出て、審査の結果を待ちます。失敗してももう一度Oral Examinationのチャンスはあると言い聞かせながらも心臓の鼓動は高まるばかりです。しばらくするとドアが開き、「合格」と告げられました。全身の力が抜け落ちました。
あれから45年、言語学界は著しく変わりました。言語研究は、メディア論、ICT(information communication technology)、AI、認知科学(cognitive science)、脳神経科学などにおける先端研究に広がりつつあります。改めてこれらComprehensive Examination for Ph.D.のWritten Preliminary Examinationの問題を読み返してみると、そのことを予見していたのではないかと思えてなりません。1975年の言語学会は圧倒的なTG(変形生成文法)に対して、各文法、GS(生成意味論)ほかの言語理論の陣営が、互いのadequacy(適宜性)を主張し、熾烈な論争を続けていました。議論は微に入り細に入りで、学徒は議論に追いつく為に多くの時間を費やしました。筆者自身その一人でした。賛否両論関係なくTGの流れについていかなければ話になりません。乗る電車の方向が違うだけで、TGというプラットフォームにみなが立たされていたような錯覚に陥りました。TGなど有力な理論についての知識は豊かになるものの、他の言語理論についての知識は乏しくなります。TGの言語論は統語論中心で、「言語をヒト特有の(species-specific)先天的(innate)能力である」と考えて言語の普遍性(linguistic universals)を求めました。但し、統語論的普遍性に終始しました。Roman Jakobsonが強調する「コミュニケーションの一環としての言語論」から見れば、「木を見て森を見ず」になってしまいます。それを危惧したのか、これらの質問には古今東西の言語論に目を向けさせようという姿勢があります。2021年現在でも新鮮で見識ある質問ではないでしょうか。(*12)
その2年ほど前のことです。この試験に合格した女性が喜びのあまり、“Here, have one! I’ve passed the Ph.D. Comp!”と言いながら、籠に入れたリンゴを往来で配って歩いたそうです。分かる気がしました。兎にも角にもこれでPh.D. Dissertationを書く資格ができた訳です。友達を集めて合格を告げ、夜遅くまで気勢を揚げました。1975年明けからよく耳にしたNeil Sedakaのリバイバル・ヒットソング“Laughter in the Rain”を聞くとあの一年が浮かんできます。メタファーとしては「土砂降りの雨の中」(in the rain)に相応しい一年で、しかし、最後は笑い(laughter)で締めくくれました。
(2021年4月20日記)
(*1)第145回目と第147回目で述べた通り、1970年代のGUのDepartment of Linguisticsの成績評価はとても厳しかったです。GPAで3.0(平均B)で合格ですが、4.0(平均A)を維持できないと勝ち残れないという雰囲気が漂い、このSemester正式登録4科目でもAを取り、全24科目GPA4.0を目標にしました。
(*2)このSeminarの履修条件は、Psycholinguistics-Child LanguageとPsycholinguistics-Language Pathologyを履修し終えていることでしたが、UH TESLで履修したSteinberg先生のPsycholinguisticsをもって充足すると判断され、聴講できました。後にneurology(脳神経学)に広げ、本コラムで紹介した言語・コミュニケーション関係の著書に繋げました。
(*3)UH TESLで1972年Fall Semesterに同じテーマを扱うTeaching English as a Second Languageを取りましたが、研究休暇中のTESL経験豊かなTed Plaister先生ではなく、経験が浅い代講者によるもので内容不十分でした。そのことをLado先生に伝えて聴講を許可されました。長年TESLをリードしてきた有無を言わせぬ経歴を基に内容に満ちた授業でした。
(*4)先生から直接聞いたのか、日本語を教えていた関係で知り合った外国語教員から聞いたのか定かでありません。
(*5)“The Sociolinguistic Profile of Brussels.” (Yuji Suzuki. 1981. The Hiyoshi Review No. 27. Keio University)および「多言語社会の実態と苦悩」(鈴木佑治. 1999. Keio SFC Review No.5. Keio University)の2点は、Sociolinguistics Ⅱで取り上げた学術記事を参考に書いたものです。
(*6)第142回と第144回を参照してください。
(*7)SLL付属英語研修Programで、GU正規のプログラムではなく、誰でも受講できました。講師はM.S.やPh.D. courses在籍の母語話者で、アメリカの大学、大学院を目指す受講生が多く、筆者にもよく相談に来ました。
(*8)筆者がGUに在籍した1973年〜1978年時点での事です。現在については定かではありません。
(*9)残念ながら、筆者が受験した1975年Fall Semester実施の試験問題が手元にありません。
(*10)第142回で述べた“Reading list for Ph.D.”です。言語学諸領域に関する書籍約40冊の中から幾つかランダムに選択され、出題されました。
(*11)答案用紙はカーボン紙を挟む3枚綴、1ページでカーボン紙を含めて合計6枚、力を入れて手書きをしなければなりませんでした。採点者が3人いたと聞いています。タイプライター持ち込みも許可されていたので、会場はプレスセンターのような音が響き渡っていました。
(*12)Roman Jakobsonはコミュニケーションの一部としての広義の言語論(a theory of language in communication)を提唱し、言語使用(linguistic performance=communication)を除外し、言語能力(linguistic competence = language proper)のみに焦点を当てるTG(変形生成文法)などを牽制しました。On Language, Roman Jakobson(1990. L. R. Waugh and M. Monville-Burstion, eds. Harvard U. Press) 参照してください。言語普遍性については、 Roman Jakobsonの(Child Language Aphasia and Phonological Universals1968, Mouton)も参照してください。児童の言語障害と音韻論におけるuniversalsを究明しています。多くの言語のデータを収集・観察・実証プロセス(inductive method)を踏襲し、広義の言語論(language in communication)研究の真髄が伺い知れます。文芸批評(literal critique)にも影響を与えました。

慶應義塾大学名誉教授
Yuji Suzuki, Ph.D.
Professor Emeritus, Keio University
上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏に限らず、世界の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト
2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場の設定を行うことができます。全国500以上の団体、約22万人以上の方々にご利用いただいています。


Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。