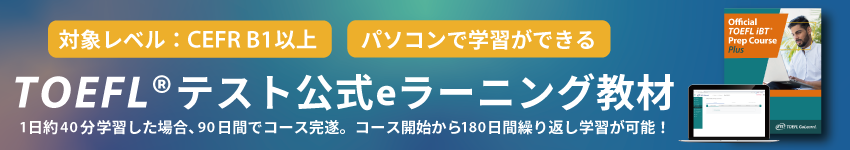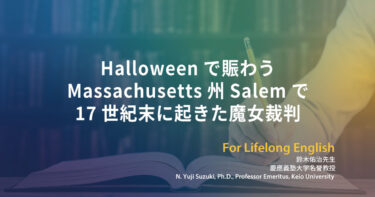第158回、第159回、第166回、第167回の続きです。言語相対性による理解、解釈の多様性は、一方、創造性(creativity)、想像性(imagination)、文学的イマジネーション、他方、多義性(polysemy)、曖昧性(ambiguity)、誤解(misunderstanding)という正と負の結果をもたらします。今回は負の部分につき、Potsdam Declarationを巡るやりとりで、日本政府側の和訳とアメリカ政府側の英訳で生じた齟齬を例に翻訳の難しさに迫ります。引用すべき資料が多いので、[1]今回(前編)と次回(後編)に分けて掲載いたします。
1945年7月26日に連合国はPotsdamにて対日共同宣言Potsdam Declarationを発しました。日本政府は宣言を和訳し、解釈し、反応します。連合国、特にアメリカ政府はその反応を英訳し、解釈し、反応します。この過程で双方に齟齬が生じました。 第158回で、HT(human translation)に比べ、MT(machine translation)の不完全さを指摘する記事を紹介しましたが、HTも完璧ではなく誤訳や齟齬を免れず、過信は禁物であることを示す一例です。
この宣言を巡る状況的法性(situational modality)を探るため、ポツダム宣言「発表後の反応」から大まかな流れをまとめます。
ポツダム宣言「発表後の反応」より抜粋・編集(筆者)
この毎日新聞、朝日新聞で報道された「黙殺 (Mokusatsu) 」は、日本の国家代表通信社である同盟通信社で“ignore”、また、ロイターとAP通信では“reject”と翻訳されました。そのことに関連し、この翻訳が同年8月6日の広島市、ついで、8月9日の長崎市への原爆投下の悲劇に繋がったという説、 [2] そして、上記の記事のように、それとは無関係に、「トルーマン大統領は、7月25日の日記に、日本がポツダム宣言を受諾しないことを確信していると記載しており、日本側の拒否は折り込み済みで、むしろ宣言のみによる降伏ではなく、宣言の拒否が原子爆弾による核攻撃を正当化し、また組み合わせて降伏の効果が生まれると考えていた」とする説などがあります。日米報道機関の間で使用した用語の誤訳なのか、はたまた、政治的思惑なのか、今後も政治学者や歴史学者による検証が続くと思います。同時に、宣言受諾直後の日本政府内での一連の議論と決議の基軸となった条約局課長下田武三による宣言の日本語訳の検証も必要です。原文がどう理解されどう翻訳されたか、東郷重徳外務大臣、鈴木貫太郎首相、陸軍関係者らの解釈・反応はまちまちで、それぞれがどのように理解しそうした反応になったのか気になります。以下、言語コミュニケーション論から一考します。
そもそも宣言/布告(declaration)とは、言語哲学者J.L. AustinがHow to Do Things with Wordsで提唱した遂行文(performative sentences/performatives )の一種です。[3] 遂行文(performatives)とは、その発信が単なる叙述・報告ではなく(“do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all”)、真偽でもなく( “are not ‘true’ or ‘false’”)、ある行為そのものの(“uttering of the sentence is, or is a part of, an action”)となる文のことです。結婚式で発せられる、新郎の“I,___, take thee, ____, to be my wedded wife.” そして、新婦の“I,___, take thee, ____, to be my wedded husband.”は、結婚という行為そのものです。進水式で発せられる“I name this ship Queen Elizabeth”は当該の船の命名という行為そのものです。これらの例はいずれも宣言 (declaration)という遂行文の一種です。1941年のルーズベルト大統領のPresident Franklin D. Roosevelt Declares War on Japan (Full Speech) | War Archives においては、最後の文“On Sunday, December 7, 1941, A state of war has existed between the United State and the Japanese empire.”をもって宣戦布告という宣言行為が成立しました。
遂行文の統語構造は、通常一人称主語Iと遂行動詞(performative verb, 例 “declare” 、“bet”、“name”)の直説法一人称単数現在能動形で成る肯定文です。ただし、それは原則で、上例の宣戦布告の遂行文のようにそうでない場合もあります。Austinの理論の影響を受け、遂行文(performatives)を言行為(speech acts)と言い換えてspeech act theory (Speech Acts Theory and Pragmatics) [4]に発展させたJohn Searleは、“Indirect Speech Acts”(1975.In Syntax and Semantics Vol. 3 Peter Cole and Jerry Morgan eds. pp.59-83)[5]と称する論文で、二人称の主語、遂行動詞ではない動詞、疑問形、否定形、などの統語構造を持つ文が、間接的に遂行文となる例を列挙しています。 Speech Act Theoryと称する無料サイトはSearleのspeech actsを下表のように分類しています。
The performative categories
| Category | Action | Example |
| Representatives(陳述) | Tell how things are | Concluding |
| Directives(指令) | Encourage action | Requesting |
| Commissives(約束) | Commit speaker to actio | Promising |
| Expressives(心理的表出) | Express psychological state | Thanking |
| Declarations(宣言) | Change the state of affairs | Christening |
広い分野で研究されており、Speech Actsにもう少し詳しい説明があります。
Potsdam Declarationは、上例の宣戦布告と同様、Searle のことばを借りるとDeclaration(宣言)というカテゴリーに属する典型的な遂行文です。一般的に外交上の取り決めは遂行文で構成されていると言えます。その意味では国が定める法律そのものが、禁止、許可、その他各種の遂行文で構成されていると言っても過言ではないでしょう。アメリカでは州議会議員、連邦議会議員は、法律を造るlawmakersと称され遂行文を心得ているものと思えます。多くは法科大学院(law schools)を卒業し弁護士(lawyers)の資格を持っています。Speech Acts in Linguisticsと称するサイトを見ると、彼らの多くは、中・高等学校、大学で履修するpublic speaking coursesでspeech actsを学んでいるように思えます。
改めてPotsdam Declaration を見てみましょう。一人称代名詞(“I”/ “we”)+宣言遂行動詞(declaratory performative verb, e.g. “declare”)を有するDeclaration(宣言)的遂行文らしきものは見当たりません。13項の “We call upon the government of Japan…”は確かに遂行文ですが、遂行動詞“call upon”では、有無を言わせぬ強制力を持つDeclaration(宣言)と比べ強制力が劣る Directive(要求)になってしまいます。要求された内容を遂行するかどうかは相手、ここでは、日本政府の判断次第です。ただ、この文を読んだ英語母語話者は、司令(commandment)、命令(order)に近い威圧を感ずる筈です。“We call upon violators to pay fines immediately, or we will confiscate their cars.”という文のように、命令されたことを果たさないと罰、または、報復があることを察知するでしょう。
他の文にも同じような高圧的な力(force)が感じ取れます。例えば、1項の “Japan shall be given the opportunity to end the war.” などの法助動詞“shall”や、5項の“We will not deviate from them.”などの“will”です。法助動詞“shall”は、“Shall I…”とか“Shall we…?”のように、現在のアメリカ英語ではごく限られたケースでしか使われません。殆どの場合、“will”にとって代わられています。詳しくはG. N. LeechのMeaning and the English Verb の4章“The Modal Auxiliaries”に現代英語の法助動詞の用法の解説があります。[6]以下、本稿テーマに関係する部分のみ要約します。
“Will”も“shall”もfuture time(未来の時)を意味する法助動詞[7]であると同時に、意志(volition)や予測(prediction as in “That will be the milkman.”)を意味する法助動詞です。“Will”も“shall”も意志(volition)を意味し、それぞれ、weak volition (弱い意志=意欲willingness)、stronger volition (強い意志=主張insistence)、intermediate volition (中間的意志=意向intention)に細分できます。しかし、決定的な違いは、“will”は文の主語(subject)の意志であるのに対し、“shall”は文の話者(speaker)の意志であることです。以下まとめます。TOEFL iBTテストを受験する読者は抑えておきましょう。
“My chauffeur will help you.” (Weak volition = the subject’s willingness=My chauffeur is willing to help you.)
“He will go swimming in dangerous waters.”(Strong volition=the subject’s insistence=He insists on going swimming…)
“I will write tomorrow.” (Intermediate volition =the subject’s intention= I intend to write.)[Volitional Shall=The Speaker’s Volition]
“Good dog, you shall have a bone when we get home.” (Weak volition = the speaker’s willingness = I, the speaker, am willing for you to have a bone…)
“You shall obey my orders.” (Strong volition = the speaker’s volition = I, the speaker, insist that you obey my order.)
“I shall write tomorrow.” (Intermediate volition = the speaker’s intention = I, the speaker, intend to write tomorrow.)
Leechは前者をthe subject-oriented(主語指向的)、 後者をthe speaker-oriented(話者指向的)と称しています。同じことが 許可(permission)の“can”と“may”、義務(obligation)の“have to”と“must”にも当てはまります。
“You may go now.” (The speaker-oriented permission=I, the speaker, permit you to go now.)
“You have to go now.” (The subject-oriented = You are compelled to go now.)
“You must go now.” (The speaker-oriented = I, the speaker, compel you to go now.)
即ち、これらthe speaker-orientedとされているvolitional shall、must of compelling/obligation(義務)そしてmay of permissionは、その深層意味構造では、I/weの第一人称主語、そして、insist/compel/permitなどの遂行動詞(performative verbs)、直説法現在などの統語的特徴を兼ね備えた遂行文(performatives)、すなわち、Searleの言行為(speech acts)であることが分かります。上述したSpeech Act Theoryに当てはめると、must of obligation/compellingはまさに Declaration(宣言)のカテゴリーに当てはまりますが、volitional shallに関しては、それに当てはまるのはthe speaker’s strong volition/insistenceの“shall”で、the speaker’s weak volition=willingnessの“shall”とthe speaker’s intermediate intentionの“shall”は、前者がExpressive
(心理表出)そして後者がDirectives(要求)のカテゴリーに当てはまります。また、may of permissionはCommissive(約束)のカテゴリーに属します。
こうしてみると、Potsdam Declarationは、これら5種の遂行文(performative)のカテゴリーで構成され、特に、Declaration(宣言)のカテゴリーに属する文で構成されていることが分かります。宣言文の大枠こそRepresentative(結論)のカタゴリーですが、Declaration(宣言)のカテゴリーに属する shall of the speaker’s insistence とmust of the speaker’s compellingが、この宣言全体の屋台骨を支えています。
上述のLeech (1971)は、この用法について次のように述べています。
Nowadays this archaic usage survives in legal and quasi-legal documents, such as rules for card games and academic dress: A player who bids incorrectly shall forfeit fifty points; The hood shall be of scarlet cloth, with a silk liming of the colour of the faculty. (Leech 1971, p81)
すなわち、主語が2人称または3人称とこの用法の“shall”との組み合わせは、支配、優勢、高慢という響き(overtones of imperiousness )が強く、民主、平等を謳う現在社会(1971年近辺以降の)で話される英語では、古臭い印象を与える、よって、欽定訳聖書(The Authorized Version of the Bible)、別称、King James 版聖書や、法律[9] や、各種ゲームなどのルールなどに残る程度です。この続きは次回の第168回にて。
(2022年記)
[1] アメリカ留学を考えている読者は是非読んでください。
[2] 國弘正雄氏の「日米“深化論”第4部」(1991年12月24日毎日新聞)を参照してください。
[3] A I(自然言語処理)、神経学(言語障害)の必読書です。アメリカ大学院留学希望の読者は読みましょう。関連して
[4] アメリカ大学院AI専攻では必読書です。
[5] Syntax and Semantics Vol. 3は、間接な遂行文に関連する重要な論文を集めています。同書収録のH.P. Griceの
“Logic and Conversation” (pp.41-58)は、アメリカ大学院留学を考えている読者は是非読んでおきたい論文です。
[6] 筆者も博士論文A Generative Semantic Analysis of the English Modalsで参考文献とした一冊です。英語の動詞句の構造、意味、用法を網羅しており、初版以来50年経て尚、英語学や自然言語処理研究で引用される良書です。英語の動詞(特に法助動詞)の意味は刻々と変化します。2021年現在の英語データに照らし、その変化を追うと面白い研究成果が出るでしょう。将来英語教育を目指す読者にお薦めします。
[7] 統語上の時制(tense)と意味上の時間(time)は別物です。現代英語にはフランス語のような未来時制(future tense)がありません。よって、未来の時を意味する“will”(as in “It will rain.”)、be +(about) to不定詞 (as in “I am about to go.”)、現在時制(as in “I leave tomorrow.”)を使います。本コラム第146回(catenary)を参照してください。
[8] “Must”にも遂行文(performative )として“I command you to__”の用法がありますが、現在は、遂行文(performative)ではなく中立的な用法(Circumstances oblige one to-不定詞、〜する必要がある as in “My doctor says that I must quit smoking.”)程度の意味のものが多いと思われます。同じように、“may” も遂行文(performative)として“I permit you to __”の用法がありますが、中立的な用法の“Circumstances allows you to__” as in “You may smoke in the smoking lounge.”か、“may”に代わりLeechの言う“democratic can.” as in “You can leave the flower vase on the dining table.”がよく使われているように思えます。 ただし、後述するように、Potsdam Declarationにおける“may”と“must”は遂行文(performative)の用法です。
[7] 例えば、 “Whoever commits or attempts to commit any act to obstruct, impede, or interfere with any fireman or law enforcement officer lawfully engaged in the lawful performance of his official duties incident to and during the commission of a civil disorder which in any way or degree obstructs, delays, or adversely affects commerce or the movement of any article or commodity in commerce or the or adversely affects commerce or the movement of any article or commodity in commerce or the conduct or performance of any federally protected function—Shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both. (Legal Information Institute https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/231)”

慶應義塾大学名誉教授
Yuji Suzuki, Ph.D.
Professor Emeritus, Keio University
上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。

英語圏に限らず、世界の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

自宅受験TOEFL® Essentials™テスト
2021年から自宅受験型の新しいテストとしてリリースされました。約90分の試験時間、短い即答式タスクが特徴のアダプティブ方式の導入されています。公式スコアとして留学や就活などにご利用いただけます。

TOEFL ITP®テストプログラムは、学校・企業等でご実施いただける団体向けTOEFL®テストプログラムです。団体の都合に合わせて試験日、会場、オンライン受験の設定を行うことができます。


Criterion®(クライテリオン)を授業に導入することで、課題管理、採点、フィードバック、ピア学習を効率的に行うことを可能にします。